生成AIは、ほぼ毎日使用しています。
税理士業務ついては、例えば次のような場面が想定できます。
相談の準備
お客さまからご相談をいただいたときの回答準備に使用しています。
例えば、事前に、ご自宅を売却したといった相談と分かった場合、3000万円の特別控除が検討できます。
基本的な要件はわかっていても、漏れがないか再確認が必要です。
税理士です。
個人のお客さまが、自宅の土地建物を売却されたそうです。
3000万円特別控除が使えそうですが、適用にあたり注意すべき点を教えて。
次のような、アドバイスが返ってきます。
もちろん、生成AIの間違いは想定済みです。
そのまま使うことはしていません。
例えば、次の回答にある「申告書添付書類」は誤りです。
また、「申告書B」は現在使われていません。情報が古いようです。
生成AIは間違いがあるから使わないという考えもあるかと思います。
しかし、間違いは人間であっても起こることです。
概観を把握し、個別に確認をするためのツールとして使っています。

条文の要約
以上で概要は把握できても、正確さの確認は必要となります。
生成AIの回答 → 解説書、国税庁HP → 通達 → 条文と遡っていくのが確実です。
ただ、条文や通達は、読みにくいのが難点。
正確さを期すために用語が堅く、法令の条文番号、定義などが途中に()で挿入されることもあります。
()を読み飛ばすなどの工夫をしても意味をとるのが難しいことがあります。
例えば、居住用財産の譲渡所得の特別控除は、租税特別措置法35条に規定があります。
これに対応する通達は、このようにはじまっています。
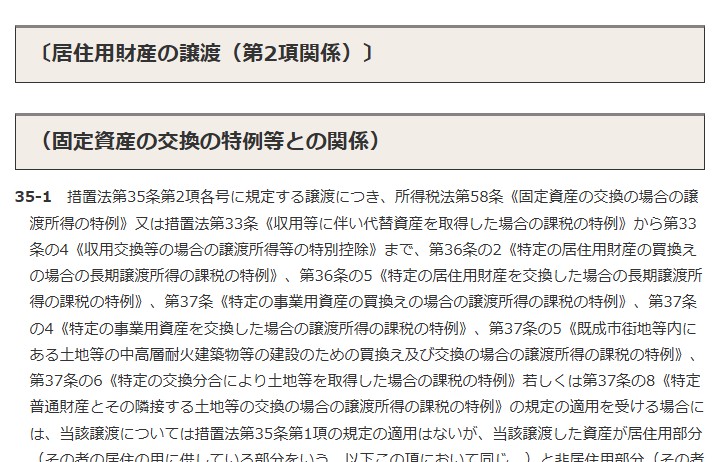
これでは、読む気がしません。
次が、通達を生成AIで要約してもらった回答です。

要領よくまとめてくれています。
文章の要約は、文章そのものだけを解釈しているように感じます。
生成AIが集めてきた資料を総合して回答するのとは異なり、信頼性は高いように思います。
条文や通達は、誤読が生じないように、論理的で緻密な構造となっています。
生成AIとの相性が良いのかもしれません。
本日のまとめ
生成AIは、プログラミング、作成資料のチェック、資料デザインの提案など、日常業務に欠かせない存在となっています。
ひとり税理士の場合、効率化や、多角的な見方を加えることは必須事項といえます。
これからも新しい使い方を探しながら、生成AIとともに仕事の質を高めていきます。


