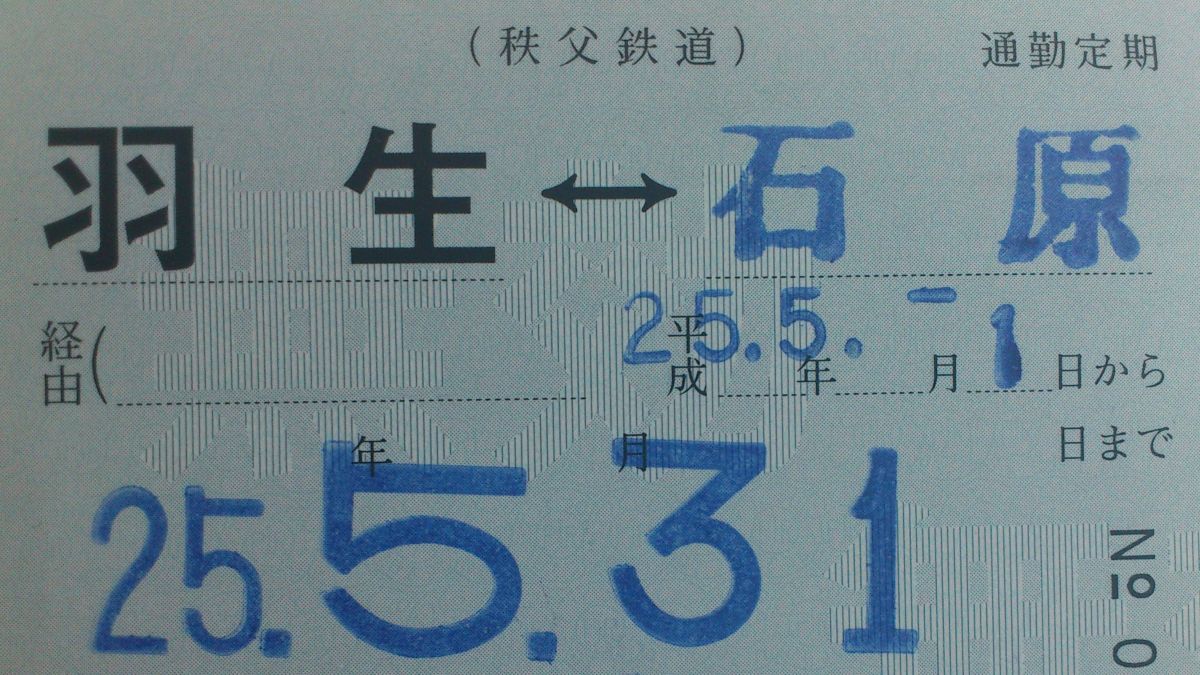このところ、遺言のご相談を多くいただいています。
先日もサポートに関与した公正証書遺言の作成に立ち会ってきたところです。
ご自身やご家族の認知機能の衰えに備えるご相談も増えてきました。
認知機能の衰えに対する準備
認知機能の衰えのご相談に関し、行政書士として状況に応じ次の5つを紹介しています。
もちろん必要であれば、税理士として相続税についてのご質問にも対応しています。
以下概要です。
細かな内容は省略していますので、利用にあたってはさらに詳細をご確認願います。
遺言書
遺言書は、基本的にご自身の財産を、どなたに、どのように引き継いでもらうかについて記す書類です。
重要な財産に関する文書であり、後日の争いを防ぐため、公正証書での作成をおすすめしています。
遺言書は認知機能が衰えると作成できないことがあります。
任意後見契約
任意後見契約とは、将来判断能力が不十分になった際に、ご自身が選んだ後見人に財産の管理、処分などを委ねる契約です。
「任意後見」とは「法定後見」に対比される用語で、後見人や委任する事務内容をご自身で選択できる点が大きく異なります。
なお、任意後見契約が発効するときには、後見人を監督する「後見監督人」が家庭裁判所により選任されます。
この後見監督人は、ご自身で選ぶことはできません。
とは言っても、ご自身の事務を行うのは任意後見人です。監督人は後見人をチェックする存在です。
法定後見よりも自由度が高いといえます。
財産管理契約
任意後見契約は判断能力が不十分になった際に発動されますが、それ以前に身体能力が衰えることがあります。
事故や病気で外出できない場合に備え、任意後見契約とあわせて財産管理契約を締結しておくことも検討できます。
尊厳死宣言
ご自身が重い病気になられ場合、延命措置を望まない意思を「尊厳死宣言」として公正証書に残すことができます。
認知機能が衰え判断能力がなくなると、延命措置に対する希望を伝えられなくなります。
死後事務委任契約
「死後事務」とは、ご逝去後の葬儀、行政手続き、各種契約の解除などの事務をいいます。
この頃は、デジタル契約やアカウントの削除なども重要になってきています。
ご家族がいない単身の方などの場合、あらかじめこのような事務をどなたかにお願いしておく必要も生じます。
こちらも認知機能が衰えると死後事務を任せることが難しくなります。
このようなお考えがあるのかについても、お尋ねすることもあります。
本日のまとめ
認知機能の衰えに備えるため、遺言、任意後見契約などいくつかの対応が可能です。
しかし、遺言以外の制度については、ご存じない方も多いように思います。
「任意後見」も「初めて聞きました」「そういう制度があるのですね」という声をよく耳にします。
制度を知らなければ、ご希望を叶えることもできません。
これらの必要性は、相談者の方の年齢、家族構成、財産などによって異なります。
認知機能に関しご相談があれば紹介し、ご相談者の判断に委ねることにしています。