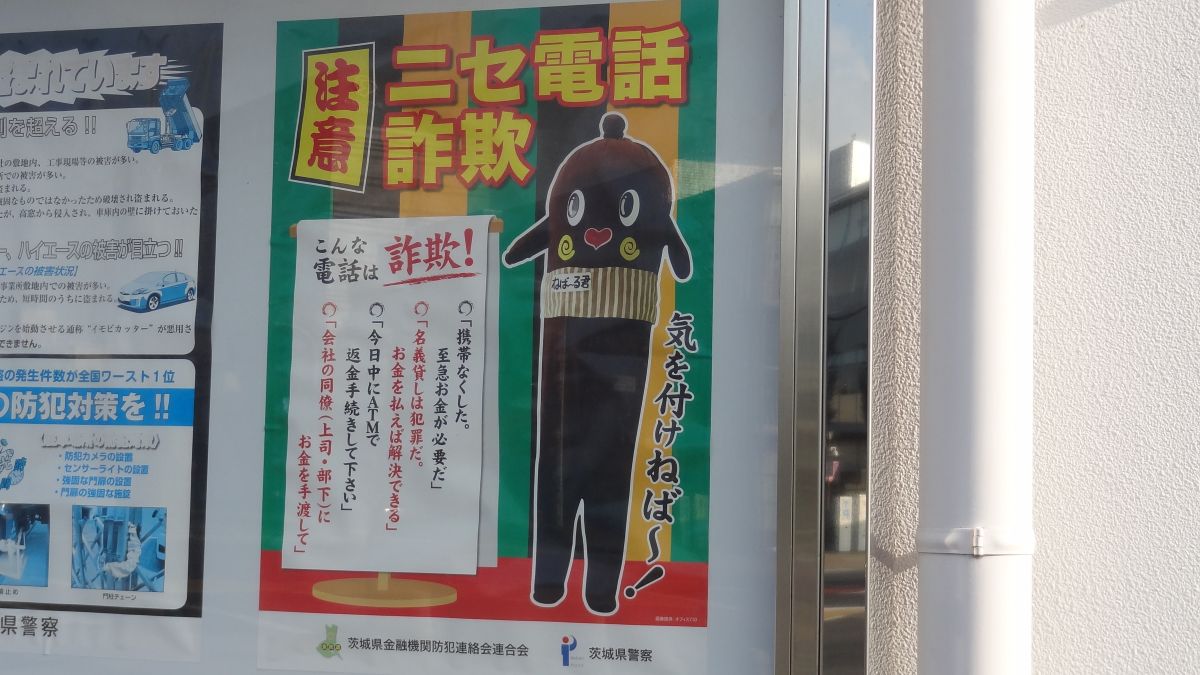このところ、佐賀県警科学捜査研究所の元職員によるDNA型鑑定不正が大きな問題となっています。
未実施のDNA鑑定を実施したように偽って報告するなど、約130件にわたって不正を重ねたという事案です。
一部は刑事事件の証拠として使われており、鑑定の信頼性を揺るがす事態となっています。
昨日も警察庁による特別監察実施の記事がありました。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO91700660S5A001C2CM0000/
科学捜査研究所職員は、高度な分析を行う専門家で、また、基本的に人事異動もありません。
その点では、財務捜査も同じです。
「専門家」の危険性
専門家は、高度な技能や能力をもち、他の人がその業務を代替することは困難です。
一般の人が容易にできない技能でなければ、専門家とはいえません。
財務捜査官が行う財務捜査と、科学捜査研究所の職員が行う鑑定には、共通点があります。
- 他の人が代替することが困難な専門的技能
- 通常、人事異動も行われず、業務がブラックボックス化しやすい
- 技能が評価の対象となる
といったことがあります。
鑑定と財務捜査の相違点
しかし、科学捜査と財務捜査には相違点もあります。
今回不正の対象となったDNAなどは、目で確認することが困難です。
これに対し、財務捜査の対象は会計帳簿などで第三者が確認することが可能です。
また、DNA型鑑定は、鑑定結果が直接犯人性につながることが多いのに対し、財務捜査の結果は犯人性を直接示すものではありません。
決算書の数字が粉飾されていることを示したとしても、実行者までを特定するものではありません。
財務捜査により算出された数値は捜査のプロセスに過ぎません。
その数値を解釈する過程を伴いますが、解釈については第三者がチェックをすることも可能です。
財務捜査のリスク
とはいえ、財務捜査についても不正、誤謬の危険性をはらんでいます。
資料の改ざん
会計帳簿類は現在はほとんどがデジタル化されています。
入手した会計帳簿を改ざんすることは、紙の資料に比べ容易になっています。
元検事が、押収したフロッピーディスクのデータを書き換えた事件も実際に起こっています。
とはいえ、会計帳簿は体系化されているため、一箇所を修正すると他の箇所の修正も必要となります。
また、デジタル証拠は通常複写して入手するため、原本との比較も可能です。
資料の誤読、誤入力
財務捜査では、原本となる資料を確認し、その内容を基に別の資料を作成することがよくあります。
例えば、資金移動状況を明らかにする場合でも、数百枚にも及ぶ原本をそのまま提示するわけではありません。
容疑者に示す場合でも、裁判に提出する場合でも、そのままでは複雑すぎてすぐには理解できません。
そこで、必要部分を抽出し、資金の流れがわかるよう加工を伴うのが通常です。
預金取引データ程度であれば入力間違いは考えにくいのですが、特殊な金融商品取引などの資料では読解が難しいこともあります。
理解不足による誤入力も実際に起こっており、平成15年10月29日大阪地裁の判決でも指摘がされています。
このような誤りについては、第三者のチェックも難しくなります。
誤判断
財務捜査により得られた数値に誤りがなくても、分析結果については判断が介入します。
複数の見方ができるのに、一つの見方だけで結論を出してしまう可能性があります。
例えば、一般的に会社の自己資本比率が低い会社は財務健全性が低いと評価されます。
借金の割合が高ければ、支払利息も多くなりそのような見方は一定の妥当性があります。
自己資本であれば、借入金のように返済の義務もありません。
ただこの評価は、日本の大多数を占める同族会社には通用しても、上場会社の場合には当てはまらないこともあります。
外部株主は株価低下のリスクを負っているため、通常、市場金利以上の配当を要求することになります。
つまり、会社にとって、増資よりも銀行借入の方が安く済むこともあります。
自己資本比率が低いということだけで財務健全性を評価することは、ミスリードの可能性があります。
これは、他の数値の解釈でも起こりうることです。
本日のまとめ
財務捜査は、科学捜査と同様に専門性が高く、捜査不正が起こる可能性も秘めています。
しかし、財務捜査は、元資料があるうえ、算出した数値によって犯人性が判断されるわけでもありません。
その点では、同一視はできません。
しかし、ブラックボックスになりやすいのも事実です。
故意、過失を問わず、どのような捜査であっても、誤りの可能は秘めているように感じます。