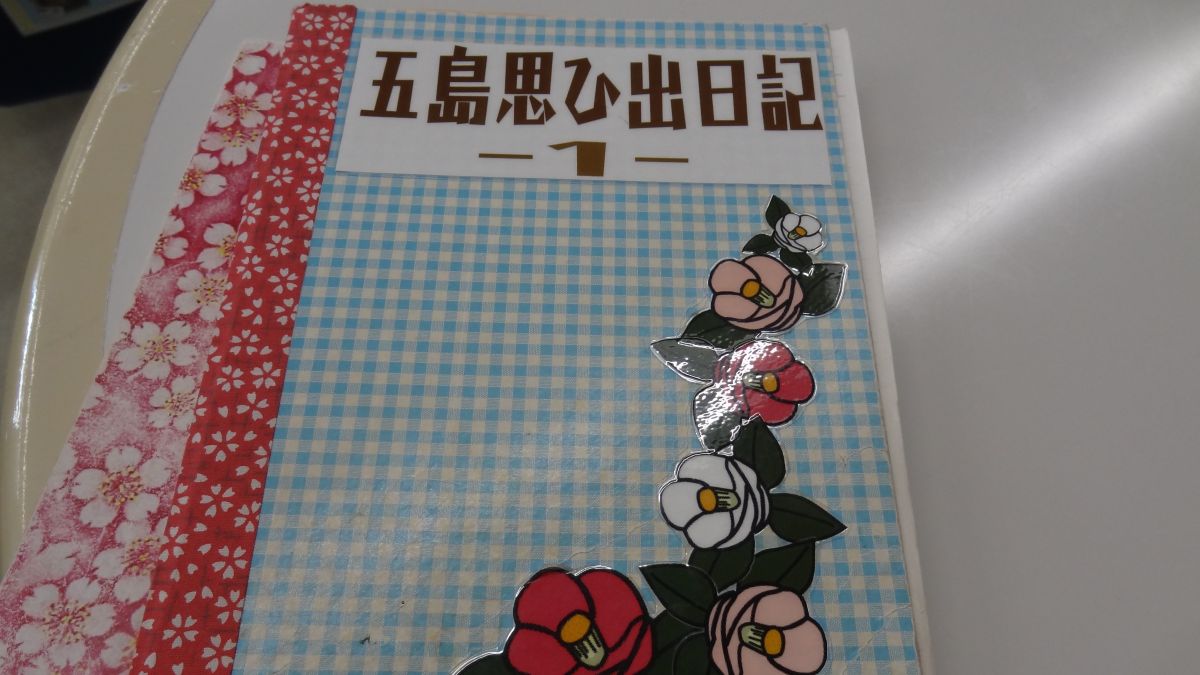財務捜査という言葉ができたのは、確認できる範囲では平成6年。
警察の歴史からすると、比較的新しい言葉です。
しかし、それ以前から帳簿による捜査は行われていたはずです。
「財務捜査」が誕生する前は、どのように財務捜査を行っていたのでしょうか。
「財務捜査」の登場
「財務捜査」という言葉が登場したのは、財務捜査官が初めて採用された平成6年の頃だと思います。
国会図書館の蔵書検索を行うと、雑誌「警察時報」平成6年7月号に「財務捜査官の採用について」と題する記事が初出です。
また、「国会会議録検索システム」で確認すると、平成8年6月に住専問題への対応に関し「財務捜査官」という答弁が見られます。
警察活動全般を紹介する「警察白書」に「財務捜査」が登場するのは平成10年版。
おそらく、この頃から財務捜査という用語が広まってきたのだろうと思います。
財務捜査とは、金銭が絡む事件について帳簿や決算書を元にした事件捜査をいいます。
代表的には、詐欺、横領、特別背任、贈収賄といった知能犯事件が関係します。
また、保険金目的の殺人事件、強盗殺人事件でも財務捜査が必要となることがあります。
これら事件捜査は、財務捜査という言葉ができるより前から存在していました。
「財務捜査」誕生前
過去の警察白書を見ると、財務捜査という言葉が登場する前は、「帳簿捜査」「財務解析」という用語を使っていたようです。
実際、私が採用された平成11年当時も「財務解析」という言葉をよく耳にしました。
昔の「帳簿捜査」「財務解析」と、今の「財務捜査」は言葉もそうですが、捜査手法も違っていたように感じます。
大きく言えば、
- 「財務捜査」より前 … 先に供述を得て、その後帳簿を確認する
- 「財務捜査」以後 … 帳簿を確認して、供述を得る
というイメージです。
「財務捜査」より前は、容疑者や関係者を取り調べ、そこから帳簿内容を確認する。
「財務捜査」以後は、帳簿で不審点を見つけ、その内容を供述で確認する。
という感じでしょうか。
実際に昔の捜査を体験したわけではないので、先輩方の話や、捜査書類を見て感じた私の感覚になります。
しかし単に私だけの感覚とも言えません。
昭和54年に元検事の河井信太郎が書いた「検察読本」には、一部の警察官の最も悪い点として、帳簿を見ないで取り調べを行うことだとして、贈賄事件を例にして書いています(同書84ページ~)。
このくだりは結構具体的で、実際このような捜査が行われていたのだろうと思います。
もちろん、「財務捜査」より前であっても、帳簿で不審点を見つける捜査もあったと思います。
ただ、大きなくくりとしては、「財務捜査」の誕生後は、言葉も捜査手法も大きく変わったように感じます。
本日のまとめ
「財務捜査」が誕生したことにより、物を基本とした捜査手法へと変わったように思います。
理由はいくつかあると思います。
- 公認会計士、税理士といった会計専門家を採用したことで、帳簿の理解が深まった。
- 志布志事件などを通じ、過度な取り調べが問題視されるようになった。
ことなどが関係しているのだろうと思います。
現在では、客観証拠の重要性が高くなっていると感じます。
その点でも、「財務捜査」の意義は今後も増すことと思っています。