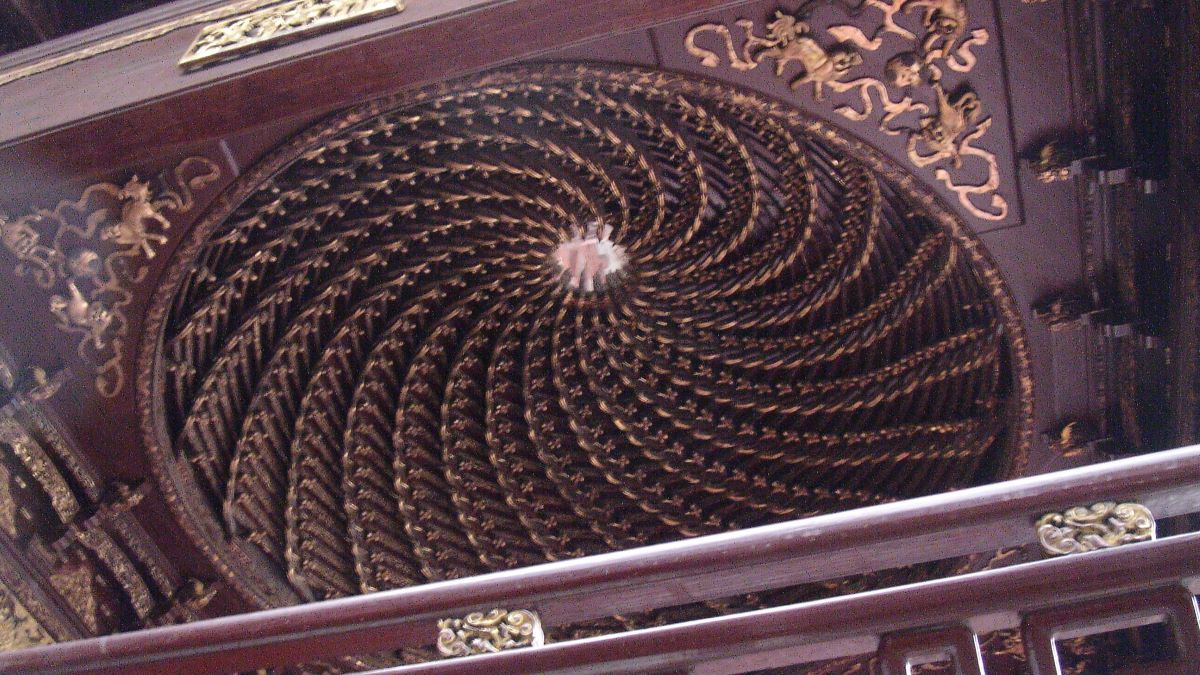報道によると、背任罪の疑いで逮捕されていた東京女子医大の元理事長が別の背任罪の容疑で再逮捕されたとのことです。
前回の逮捕、そして今回の再逮捕とも、建築士に支払われた資金が元理事長に側近の元職員を介して還流していたとのこと。
典型的な背任事件と感じます。
背任罪の構成要件
背任事件(株式会社などに適用される特別背任事件も同様です。)の構成要件は、大きく、
- 他人のためにその事務を処理する者が(身分)
- 自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で(図利加害目的)
- その任務に背く行為をし(任務違背)
- 本人に財産上の損害を加えた(損害の発生)
となっています。
大学の理事長は、学校法人から委任を受け、学校法人のために忠実に事務を行う義務を負っています。
その任務に背き自己の利益を図った場合、背任罪に問われることになります。
事件の構図
背任罪の適用でしばしば問題になるのが、自己または第三者の利益を図る目的の有無になります。
今回の事件の構図は、
- 大学が発注する建築工事を巡り、元理事長と関係する建築士にアドバイザー名目で報酬を支払う
- 建築士は入金された一部を現金で引き出す
- 引き出した現金を元理事長の側近の元職員に渡す
- 元職員は元理事長に現金を渡す
という流れです。
大学から支払われた資金が、建築士、元職員を介して元理事長に還流しています。
資金還流がない場合
今回は資金還流があるために、利得目的であることを示すことができます。
しかし、還流がない、あるいは、発見できない場合、立件の難易度はかなり高くなります。
例えば今回の事件でいえば、建築士へのアドバイザー報酬が高いというだけで背任罪を立件するのは難しいように思います。
理事長としては、学校の財産を無用に流出させないように、なるべく安い報酬で済む建築士に依頼する必要はあるかもしれません。
しかし、建築の業務は専門性が高く、報酬の安さだけで選ぶことはできません。
過去の実績、建築の難易度、有する専門性によって報酬が変わってくることは避けられません。
このときに、その報酬が高いか安いかを議論するのは難しいところがあります。
今回の事件では、実際の業務は別の建築士が行っており、依頼内容に実態はなかったとも言われています。
しかし、その別の建築士に依頼すること自体にも専門性はあるはずです。
報酬が高い、あるいは、業務の実態がないとということだけで背任罪を立件するのは難しいというのが実感です。
無用な支出が争われた背任事件として、三越事件がありますが、「有用性の対価として許容し得る限度を明らかに超えた」かどうかが判断基準となっています。
やはり背任罪のポイントとなるのは、資金の還流の有無。
還流が解明されれば、「自己の利益を図る目的」であったことが認められる可能性が大きく高まります。
また、同時に、他の要件である、任務違背、学校に損害を与えたことも立証することが可能です。
本日のまとめ
背任事件、特別背任事件捜査には、過去何度か従事したことがあります。
立件を見極める最初のポイントは、資金還流の有無です。
今回の事件は、典型的な背任事件と見受けています。